【経営者必見】資金繰りが苦しい会社が今すぐ知るべき7つの対策とは?
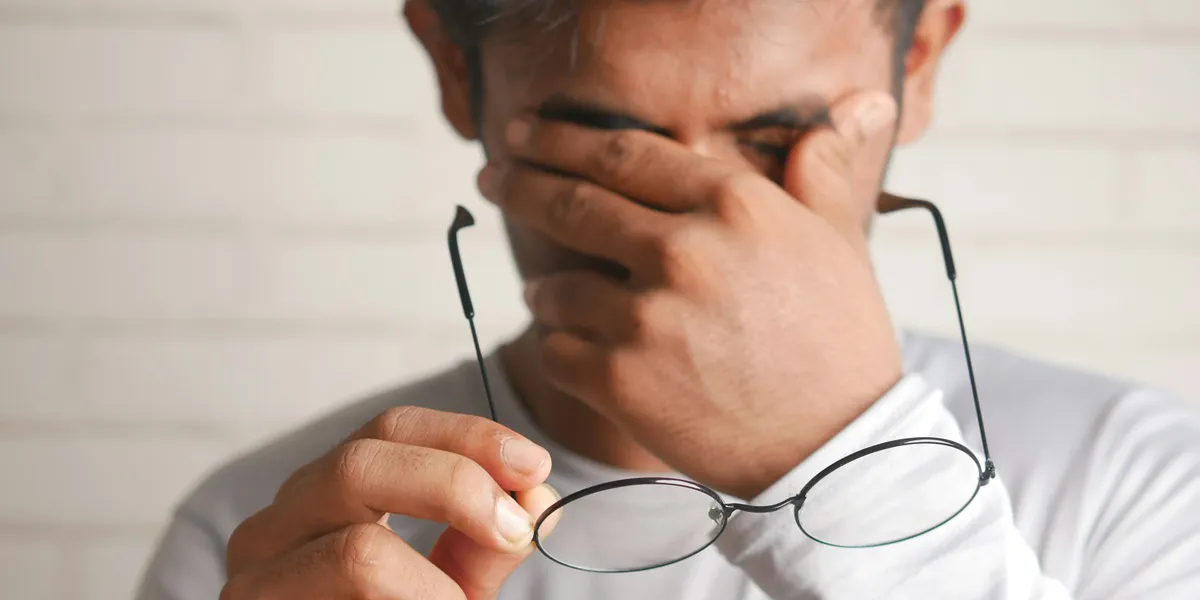
「売上はあるのに、どうして手元にお金が残らないんだろう…」
多くの経営者が抱えるこの悩み。昨今の物価高騰や人手不足、コロナ融資の返済など、中小企業を取り巻く環境は厳しさを増すばかりです。しかし、資金繰りの苦境は決して珍しいことではありません。重要なのは、問題に早く気づき、適切な対策を講じることです。
本コラムでは、資金繰りが苦しい会社が陥りやすい典型的なパターンを明らかにし、今すぐ実践できる具体的な改善策を7つの視点からご紹介します。経営者の皆様が一人で悩みを抱え込むことなく、確実な一歩を踏み出せるよう、財務コンサルタントの視点から分かりやすく解説していきます。
資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。
目次
「資金繰りが苦しい」は誰にでも起こりうる現実
資金繰りが苦しい時は、どんな優秀な経営者でも直面する可能性があります。それは決して経営能力の欠如を意味するものではなく、むしろ事業を真剣に営んでいるからこそ出くわす課題なのです。多くの経営者は、この現実を受け入れることで、より建設的な対策を講じることができるようになります。
経営者が感じる「漠然とした不安」
資金繰りの悪化は、月次試算表や決算書では利益が出ているケースであっても、仕入債務や借入金などに追われて資金が足りなくなり、黒字倒産する場合も少なくありません。「今月の支払いは何とかなるかもしれないが、来月は大丈夫だろうか」「取引先からの入金が遅れたらどうしよう」という不安が頭から離れない経営者も多いはずです。
特に中小企業の場合、経営者自身が財務や会計に苦手意識を持ち、経理担当者にまかせっきりにしている人も多く見られます。しかし、資金の流れを把握していないと、いざという時に打つ手が限られてしまいます。資金繰りの問題に気づくのが遅れ、手遅れになってしまうケースも少なくありません。
コロナ禍・物価高騰・人手不足…資金が詰まる背景
近年、日本の中小企業を取り巻く環境は、かつてないほど厳しさを増しています。新型コロナウイルスの影響で、売上が大幅に減少した企業も多く、コロナ融資の返済が厳しい場合、借り換え制度を利用する方法もあります。多くの企業がコロナ融資の返済に苦しんでいる現状があります。
加えて、急激な物価高騰により、仕入れコストや光熱費などの固定費が上昇し、利益を圧迫しています。セーフティネット貸付は日本政策金融公庫による融資制度です。社会的もしくは経済的環境の変化によって資金繰りが苦しい状況になっている事業者が利用対象になっています。このような制度が用意されているのも、多くの企業が厳しい状況に置かれている証拠です。
さらに、人手不足による人件費の上昇も重なり、経営者は二重三重の苦しみに直面しています。従業員の採用が難しくなる中、人件費は上昇し続け、派遣社員や外注費も高騰。これらすべてが資金繰りを圧迫する要因となっています。
また、予期せぬ事態が急に発生することがあります。例えば、取引先の倒産や災害、損害賠償の支払いなどが挙げられます。こうした突発的な出費も、資金繰りを一気に悪化させる原因となります。特に、主要取引先からの入金が滞ったり、急な設備の故障で想定外の修理費用が発生したりすると、たちまち資金繰りが苦しくなってしまいます。
このような状況下で、「資金繰りが苦しい」という状況は、決して特別なことではありません。むしろ、どの企業にも起こりうる現実なのです。重要なのは、早期に気づき、適切な対策を講じることです。
資金繰りが苦しい会社に共通する5つのサイン
資金繰りの悪化は、実は事前に「サイン」を発しています。これらのサインを早期に察知し、適切に対処することで、深刻な資金難を防ぐことができます。以下に、私がこれまで多くの企業を見てきた中で、特に注意すべき5つのサインをご紹介します。
売上があるのに手元資金が足りない
「売上は伸びているのに、なぜか手元にお金が残らない」というのは、資金繰りが悪化し始めた最も典型的なサインです。売上は上がっているのに利益が出ないで困っていませんか?という状況は、多くの経営者が経験する問題です。
この現象が起きる主な原因は、売掛金の回収期間が長いことにあります。1000万円の売上があり、そのうち300万円が売掛金に含まれている場合、決算書上では売上が1000万円と計上されますが、実際のお金の動きとしては700万円しか手元に残らないことになります。つまり、売上と現金の動きにはタイムラグがあり、このズレが資金繰りを圧迫するのです。
また、在庫金額が大きくなっていくと、それだけ現金化されていない資産が大きくなり、資金繰りが厳しくなります。売れない在庫を抱えることは、現金を倉庫に寝かせているのと同じことなのです。
支払い期限の交渉が常態化している
取引先に「今月の支払いを少し待ってもらえませんか?」と頻繁にお願いしている場合、それは資金繰りが既に危険水域に入っているサインです。一時的な支払い延期は許容範囲ですが、それが常態化すると信用問題に発展します。
資金繰りが悪化した際には、取引先との協議を通じて支払いのタイミングを調整することを検討しましょう。ただし、取引先との信頼関係を損なわないように注意する必要があります。支払い延期の交渉が増えるということは、資金繰りの計画性が失われ、自転車操業状態に陥っている証拠なのです。
特に従業員への給与支払いまで遅れるようになると、企業の存続自体が危ぶまれます。万が一従業員への給与支払いが遅れる場合には、離職やモチベーションの低下につながる可能性があるため、事前にしっかりと説明しましょう。
借入返済のために新たな借入をしている
これは最も危険な兆候の一つです。借入金の返済期日が迫っているため、新たな借入を行って返済に充てるという行為は、まさに「借金で借金を返す」状態です。
街金融や商工ローンは一般に10%~20%以上の金利を支払うことになりますが、ただでさえ資金繰りが厳しいところに、高金利を負担しつつ経営再建を図ることは至難の業です。高金利の借入に手を出してしまうと、雪だるま式に借入金が膨らみ、資金繰りはさらに悪化していきます。
このような状況に陥る前に、金融機関との早めの相談や、返済スケジュールの見直しを検討する必要があります。
資金繰り表が曖昧・存在しない
資金繰り表とは、会社のお金の入出金を予測し、管理するための表です。資金繰り表とは、「いつまでに」「いくら」の入金があるのか、「いつまでに」「いくら」支払う必要かを記したものです。
しかし、資金繰りに苦しむ会社の多くは、この資金繰り表が作成されていないか、あったとしても曖昧で形だけのものになっています。小規模事業者などでは作成していないことも少なくありません。また、金融機関に提出する融資のための書類として作成しているだけで、活用しきれていない企業も多いのではないでしょうか。
資金繰り表がないということは、会社の財務状況を運に任せているのと同じです。いつ資金ショートするかを予測できず、対策も後手に回ってしまいます。
社長が「なんとかなる」と感覚で判断している
最後のサインは、経営者の姿勢そのものです。「今までも何とかなってきたから、今回も大丈夫だろう」という根拠のない楽観主義は、最も危険な思考パターンです。
会社の資金繰りを円滑に回すには、社長自身が資金繰りを理解していることが何よりも大切です。しかし、社長のなかには、財務や会計に苦手意識を持ち、経理担当者にまかせっきりにしている人も多く見られます。このように数字に基づかない判断は、致命的な経営ミスにつながる可能性があります。
具体的な数字を把握せず、感覚だけで経営判断を行っていると、気づいた時には取り返しのつかない状況に陥っているかもしれません。「なんとかなる」ではなく、「なんとかする」という姿勢で、具体的な数字を見ながら早めの対策を講じることが重要です。
エクステンドでは、経営者様からの無料相談を受け付けています。早急に苦しい資金繰りを改善したいとお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。財務コンサルタントが親身になって対応致します。
資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。
見落としがちな原因と、その改善ポイント
資金繰りが悪化する原因は、表面的には見えにくいものが多くあります。日々の業務に追われていると気付きにくい「静かな資金流出」に着目することが、改善の第一歩となります。ここでは、見落としがちな4つの原因とその改善ポイントを解説します。
売掛金回収の遅れ
売掛金の回収遅延は、資金繰り悪化の最大の原因です。資金繰りを良くするためには「回収は早く、支払いは遅く」することが鉄則です。売上債権の回収サイト(回収期間)を早くし、仕入債務の支払サイト(支払期間)を遅くすることで資金繰りが楽になります。
多くの中小企業が「取引先との関係を壊したくない」という理由で、売掛金の回収を後回しにしがちです。しかし、締切日に入金されず、督促しても支払いがないような、回収できない売上債権はないでしょうか? 回収できない売上債権は資金繰りを圧迫します。
改善のポイントとしては、まず取引先ごとの支払い状況を把握し、遅延が常態化している先には早めに対応することです。具体的には、請求書発行のタイミングを早める、督促の仕組みを作る、場合によっては前受金や手付金の導入も検討すべきでしょう。
在庫過多による資金の固定化
在庫は「第二の現金」とも呼ばれますが、過剰な在庫は経営の足かせとなる重大な問題です。在庫をかかえすぎると資金繰りが悪化します。商品は購入代金支払い時にキャッシュアウトしますが、販売しなければ経費になりません。大量の在庫をかかえてしまうと、現金が少ないのに利益が出てしまうため、黒字倒産の原因になってしまいます。
特に注意すべきは、不良在庫とは、トレンドに遅れた商品や季節外れになった商品、賞味期限切れや消費期限切れになった商品など、売れないまま長期間が経過した商品のことです。不良在庫は現金化できないだけでなく、倉庫代や在庫管理の人件費など、さまざまなコストがかかります。
改善策としては、定期的な在庫の棚卸しと分析、ABC分析による在庫管理、発注点の見直しなどが挙げられます。また、不良在庫は思い切って処分し、キャッシュを回収する決断も必要です。
粗利の低い案件の受注
「売上を上げたい」という焦りから、採算性の低い案件を安易に受注してしまうことは、資金繰りを悪化させる典型的なパターンです。売上は増えても、利益が残らず、むしろ人件費や経費だけが増加してしまいます。
この問題は、売上は上がっているのに利益が出ないで困っていませんか?という状況を引き起こします。特に価格競争の激しい業界では、原価計算の甘さや見積もりの精度不足が原因となることが多いです。
改善のためには、案件ごとの原価管理を徹底し、最低限確保すべき粗利率を明確にすることが重要です。また、付加価値の高いサービスや商品開発に注力し、価格競争から脱却する戦略も検討すべきでしょう。
固定費の増加と見直し不足
固定費は経営の重石となりやすく、一度増えると削減が難しいという特徴があります。一番最初にやるべきことは、無駄な経費がないかの確認です。例えば交通費・固定費・役員以上の経費などは見落としやすいので、なるべく削減してださい。
特に見落としがちなのは、使っていないサブスクリプションサービス、過剰な事務所スペース、活用されていない会員権や保険などです。また、経費の中でも現金払いではなく、クレジットカードで支払うことができる経費については積極的に支払方法を変更しましょう。クレジットカードで支払いを行うことで、支払いを1か月ほど伸ばすことができ、資金繰りにとってプラスになります。
改善のポイントは、まず固定費の洗い出しを行い、費用対効果を定期的に検証する仕組みを作ることです。そして、変動費化できるものは変動費に、アウトソーシングできるものは外注化を検討し、柔軟な費用構造を目指すべきでしょう。
いますぐ取り組める資金繰り改善策

資金繰りの改善は一朝一夕にはいきませんが、今すぐ着手できる具体的な対策を実行することで、確実に状況を好転させることができます。ここでは、即効性のある4つの改善策をご紹介します。
資金繰り表の作成と見直し
資金繰り表の作成は、資金繰り改善の第一歩です。資金繰り表で、資金の流れを把握していれば、運転資金がショートする前に資金調達の策を考えることができます。無理な設備投資を防ぐこともできます。
資金繰り表とは、キャッシュフロー計算書や月次試算表をもとに3か月先ぐらいまでの見通しを立てましょう。この表を作成することで、将来の資金不足を予測し、事前に対策を立てることが可能になります。
具体的な作成手順としては、まず今後3か月分の売上予測と入金予定を記入し、次に仕入れや経費の支払い予定を書き込みます。特に重要なのは、予測と実績の両方を記録することです。資金繰り表には、「予測」と「実績」の項目があり、予算の項目には予測数値を、実績には実際の現金収支を記載します。
資金繰り表は、テンプレートをダウンロードすることもできるので、「資金繰り表+テンプレート」などで検索してみましょう。エクセルなどで簡単に作成できるため、まずは始めてみることが大切です。
取引条件(入金・支払)の再交渉
取引条件の見直しは、即効性のある資金繰り改善策です。ポイントは「入金を早く、支払いを遅く」です。
まず、売掛金の回収サイトを短縮する交渉から始めましょう。売上が発生して売掛金を回収する、または受取手形として回収するまでの期間が長いと、資金繰りが厳しくなってしまいます。長くなった顧客とは、支払サイトを見直し、取引先との交渉を検討しましょう。
具体的には、月末締め翌月末払いを当月末締め翌月15日払いに変更するなど、少しずつ回収サイトを短縮していきます。また、一部前払いや内金制度の導入も検討の価値があります。
一方、仕入先への支払いについては、資金繰りが悪化した際には、取引先との協議を通じて支払いのタイミングを調整することを検討しましょう。ただし、取引先との信頼関係を損なわないように注意する必要があります。支払い条件の交渉時は、誠実な説明と今後の取引継続の意思を示すことが重要です。
補助金・助成金の活用
補助金や助成金は、返済不要の資金調達方法として、資金繰りの大きな助けになります。多くの中小企業が「手続きが複雑」「うちには関係ない」と思い込んでいますが、実際には様々な支援制度が用意されています。
特に、セーフティネット貸付は日本政策金融公庫による融資制度です。社会的もしくは経済的環境の変化によって資金繰りが苦しい状況になっている事業者が利用対象になっています。このような公的支援制度は、民間金融機関よりも低金利で長期の返済が可能という特徴があります。
また、コロナ融資の返済が厳しい場合、借り換え制度を利用する方法もあります。具体的には、日本政策金融公庫のコロナ融資を受けている場合は、「公庫融資借換特例制度」を利用可能です。既存の融資と借り換えと同時に新規の融資を受けます。
助成金の情報収集は、中小企業庁のウェブサイトや地元の商工会議所、自治体の産業振興課などで行えます。申請には時間がかかるため、早めの情報収集と準備が成功の鍵となります。専門家に相談することで、自社に合った補助金・助成金を見つけやすくなるでしょう。
公的支援・専門家の力を借りるという選択肢
資金繰りの問題は、経営者一人で抱え込むべきものではありません。公的機関や専門家の支援を積極的に活用することで、客観的な視点から解決策を見出すことができます。ここでは、中小企業が利用できる主な支援機関と専門家について解説します。
商工会・信用保証協会・公庫のサポート
資金繰りに苦しむ経営者の多くは、「自分一人で何とかしなければ」と考えがちですが、公的機関には中小企業をサポートする様々な制度が用意されています。これらを活用することは、決して恥ずかしいことではありません。
まず、商工会議所や商工会は、経営相談や資金繰り支援の窓口として重要な役割を果たしています。商工会・信用保証協会・公庫のサポートを受けることで、資金繰りの改善策を具体的に検討できます。専門家による無料相談や、経営改善計画の策定支援なども行っています。
信用保証協会は、民間の金融機関からゼロゼロ融資を受けている場合は、「コロナ借換保証」制度を利用できます。保証限度額は1億円、保証期間は10年以内(据置期間5年以内)、保証料は0.2%等です。このように、中小企業が金融機関から融資を受けやすくするための保証を行っています。
日本政策金融公庫は、民間金融機関が対応しにくい案件にも柔軟に対応してくれます。資金繰りを安定させるためには、必要な時に必要な資金を調達できる体制づくりが必要です。特に、セーフティネット貸付は国民生活事業と中小企業事業の2種類があり、融資限度額や利用対象者、利率などがそれぞれ異なります。
さらに、中小企業再生支援協議会では、新型コロナ感染症特例リスケジュールを提供しています。これは、借入金の返済負担を軽減するために中小企業再生支援協議会が金融機関と経営者の間に入って借入返済をリスケジュールの養成をする制度です。専門家が無料で相談に乗ってくれるため、まずは相談してみることをお勧めします。
財務コンサルタント・税理士の活用
専門家の力を借りることは、資金繰り改善の近道です。特に財務コンサルタントや税理士は、多くの企業の資金繰り改善を支援してきた経験から、具体的で実効性のあるアドバイスを提供してくれます。
しかし、資金繰りが苦しいと、どこから手をつけていいか迷ってしまうこともあるかもしれません。当事務所では、長年にわたり中小企業の経営者様に寄り添って参りましたので、資金繰りに関するアドバイスも可能です。必要であれば資金繰り計画を作成するお手伝いも致します。このように、専門家は現状分析から具体的な改善策の提案、実行支援までトータルでサポートしてくれます。
財務コンサルタントを活用するメリットは、客観的な視点で会社の財務状況を分析してもらえることです。資金繰り(運転資金)のための資金調達方法として、最も一般的なのは金融機関からの借入です。日頃から金融機関・支援機関と良好な関係を築き、自社の経営状況についての理解を求めておきましょう。コンサルタントは、金融機関との交渉や資金調達の支援も行ってくれます。
税理士の場合は、日常的な記帳や決算業務だけでなく、中には資金繰り表の作成にも対応してくれます。特に顧問税理士は、会社の状況を継続的に把握しているため、より的確なアドバイスが期待できます。
専門家の選び方のポイントは、資金繰り改善の実績があるか、中小企業の支援経験が豊富かという点です。また、相談しやすい人柄かどうかも重要です。初回相談は無料の場合も多いので、まずは複数の専門家に相談してみることをお勧めします。
専門家への相談は費用がかかりますが、その投資効果は計り知れません。早期の相談により、より大きな損失を防ぐことができるからです。資金繰りの改善は、経営者の判断力と実行力、そして適切な外部支援の組み合わせによって実現します。自社だけでは解決が難しいと感じたら、迷わず専門家に相談することをお勧めします。
エクステンドでは、経営者様からの無料相談を受け付けています。新たな資金調達を成功させたい、返済・資金繰りなどの財務でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。財務コンサルタントが親身になって対応致します。
資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。
「資金繰りに追われない会社」になるために必要な視点
資金繰りに追われない会社になるためには、「利益」から「キャッシュ」へ経営の視点を転換することが不可欠です。利益を追求することは営利企業にとって大事なことですが、売掛金などの売上債権の回収サイトと仕入債務の支払サイトを見直し、無理のない借入金の返済計画を立て、資金をショートさせないことが重要です。
多くの経営者が陥りがちな誤解は、「損益計算書の利益が出ていれば問題ない」という考え方です。しかし、いくら利益が出ていたとしても、資金の流れを把握していなければ支出が重なった時に破綻してしまいます。黒字経営であっても、大きな支出や仕入れで支払いができなくて倒産してしまうのはこのためです。
キャッシュ重視の経営を実現するためには、キャッシュフロー計算書の読み方を理解し、定期的にチェックする習慣をつけることが重要です。営業活動、投資活動、財務活動それぞれのキャッシュフローを把握し、現金がどこで増え、どこで減っているのかを明確にしましょう。
経営数値の見える化と共有
経営数値の見える化は、資金繰り改善の基盤となります。会社の体力を認識するために決算書を理解できるようになりましょう。経営者が数字を把握するだけでなく、必要な範囲で従業員とも共有することで、全社一丸となった資金繰り改善が可能になります。
具体的な見える化の手法としては、まず月次決算の導入が挙げられます。資金繰り表には、「予測」と「実績」の項目があり、予算の項目には予測数値を、実績には実際の現金収支を記載します。月次で実績を把握することで、問題の早期発見と迅速な対応が可能になります。
また、お金の流れを可視化することで、意識も大きく変わってくるでしょう。従業員にも適切な範囲で情報を共有し、売掛金の回収や経費節減への協力を促すことで、組織全体で資金繰りを意識する文化を醸成できます。
攻めと守りの資金計画のバランス
資金繰りに追われない会社になるためには、「守り」の資金管理と「攻め」の成長投資のバランスが重要です。守りばかりでは事業の成長が止まり、攻めすぎると資金ショートのリスクが高まります。
「守り」の資金計画としては、資金繰りを安定させるためには、必要な時に必要な資金を調達できる体制づくりが必要です。具体的には、手元資金(現預金)を月商の2〜3ヶ月分確保する、緊急時の資金調達ルートを複数持つなどの対策が有効です。
「攻め」の資金計画では、無理な設備投資を防ぐこともできます。成長投資を行う際は、必ず投資回収計画を立て、資金繰りへの影響をシミュレーションしましょう。投資の優先順位を明確にし、段階的な投資計画を立てることが重要です。
また、突発的なリスクに対応するために、長期的なリスクファインスとして「損害保険」の活用も重要です。予期せぬ事態に備えることで、資金繰りへの影響を最小限に抑えることができます。
バランスの取れた資金計画を実行するためには、定期的な資金繰り予測と実績の比較分析、PDCAサイクルの確立が欠かせません。計画と実績の差異を分析し、必要に応じて計画を修正することで、持続可能な経営体質を構築できるのです。
まとめ|苦しい今を乗り越えるためにできることから始めよう
ここまで、資金繰りが苦しい会社の特徴から具体的な改善策まで見てきました。今、資金繰りに苦しんでいる経営者の皆さんに伝えたいのは、「必ず乗り越えられる」ということです。
資金繰りが苦しいときには、金融機関からの追加融資を検討する前に今すぐできることからやりましょう。一つ一つの効果は高くないかもしれませんが、継続して見直しを行うことで、資金繰りの悪化が起こりにくい財務体質に変化していきます。まずは小さな一歩から始めることが重要です。
具体的には、今日からできる資金繰り表の作成、明日にでも取引先との支払い条件の見直し交渉を始めてみましょう。このような資金繰り表を作成して活用することで、資金繰りが苦しい状況から脱却することができ、健全な資金繰りに立て直せるよう願っております。
また、一人で抱え込まずに専門家や公的機関のサポートを積極的に活用することも大切です。資金繰りを安定させるためには、必要な時に必要な資金を調達できる体制づくりが必要です。商工会議所や金融機関、財務コンサルタントなど、様々な支援者があなたの味方になってくれます。
特に重要なのは、資金繰りの問題に早期に気づき、迅速に対応することです。早い段階で資金繰りの悪化に気付くためにも、普段から経営状態をチェックし、事前に備えておくようにおすすめします。問題を先送りにすることなく、今すぐ行動を起こしましょう。
そして、長引く不況の中、経営者はほぼすべてが「資金繰りが苦しい…」と感じているといっても過言ではありません。つまり、あなただけが特別に苦しいわけではないのです。多くの経営者が同じ悩みを抱え、そして乗り越えています。
最後に、もし、どこから手をつけていいか分からない、自社だけでは解決が難しいと感じられた場合は、まずは財務コンサルタントへの相談をご検討ください。経験豊富な財務コンサルタントの第三者の客観的な視点が、打開策を見出してくれることもあります。
エクステンドでは、経営者からの無料相談を受け付けています。新たな資金調達を得たいや、返済・資金繰りなどの財務でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。財務コンサルタントが親身になって対応致します。









