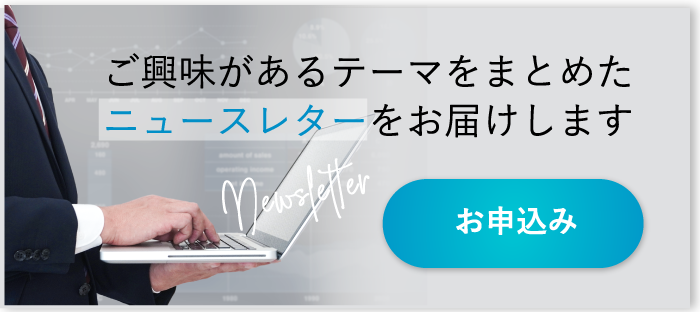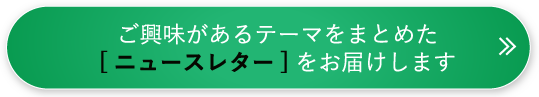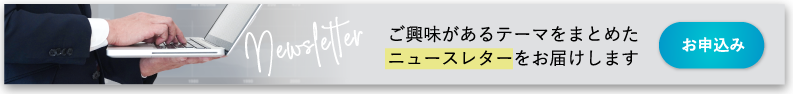2021.10.27
事業計画策定の要諦 体裁の良い数値計画が事業計画ではない
きれいな数値の事業計画をよく拝見します。表計算ソフトで立派な表ができると、それで満足してしまい、「この通りいくだろう」と考えてしまう方が多いのです。
ここでは、事業計画について3つの視点をお伝えします。
計画は計画通りにはいかない
ひとつ目に、計画は計画通りにはいかないという話をします。事業計画の本質について、ヘンリー・ミンツバーグという経営学者の言葉が腑に落ちたので引用します。彼は「理論家とは一線を画す異色の経営学者」と言われている人物です。
現実的には、ある程度先を考えておきながら適時対応していくことになるだろう。実現された戦略は最初から明確に意図したものではなく、行動のひとつひとつが集積され、その都度学習する過程で戦略の一貫性やパターンが形成される。
私はこれを「事業計画は結局後付け」ということだと解釈しています。実際に私の経験上、3年前に立てた計画が、3年後そのまま実行されてるケースはありません。うまくいく事業というのは想像を超えてはるかに良くなっています。むしろ計画通りにいってはいけないのです。そこに新しい創造などが何もないことになりますから。
例えばある急成長のプロセスを経た会社の例をお話ししましょう。売上高が10億円ぐらいだった会社が5年後200億円の会社に成長を遂げました。これは、単純に一つの事業が伸びた訳でなく。M&Aの組み合わせでここまで成長した訳ですが、大事なことは大きな目標を持ち、目の前に現れることへの対処をその都度考えて調整しながらそこに到達したことが、スタート時から想像もしなかった企業になったということです。
成功した経営者は著書や講演会などで、当初の計画通りにいったように語るので注意してください。うまくいった後、記憶を辿りながら論理的に整理をしていくので一貫性があるように見えるだけです。これを鵜呑みにし、あの経営者が言うのだから間違いない、やはり計画通りいくのだと思ってはいけません。特に財務力の弱い会社の経営者が会社をつぶす原因はここにあると思っています。
計画を立てる時点では、いかに目が良い人でも1キロ先しか見えないはずです。そこから1km進むから、1km先からの視点を持てるのです。さらに、スタート時点では標高0メートルだったのが、標高が上がるにつれ高い位置から景色が見えるようになります。スタート地点では見えなかった奥行きが見えてくるのです。
そのときに見る景色と、スタートの地点で見る景色が変わっていて当然で、その標高と距離が生まれた時から新しい計画をたてなければいけません。
このように考えれば計画は連続的に変わっていくのが当然で、その時点における最善の手を打ち続けていくことが経営にとって一番重要なことです。スタート地点から何も計画が変わっていないことのほうが問題なのです。予定通りいかなくて当然、予定通りいくのがおかしいのです。むしろ、計画通りにいかないことを見越して、その都度調整を図るための経営指標があることが大切です。
事業計画とはまず事業立地である
二つ目に事業計画とはまず事業立地である、ということです。No.2でご紹介した三品和広教授の言葉を引用します。
事業の根底には立地(誰に何を売るか)があって、その上に構え(出荷するものをいかに人手で顧客に届けるか) 製品(いかに個別製品を魅力的にしたてるか)管理(いかに品質・原価・納期を守るか)が重層構造をなしている。~中期経営計画などで立地や構えに手をつけることなく、製品の刷新や管理の強化を打ち出している企業は数多くあるが、この次元で動き出したところで、高収益への転換に結びついた事例はほとんどない
つまり、事業の根底には立地があり、事業計画とはまずは事業立地……事業の型や収益の型を考えることだと言っているのです。数値表を出すのはその後です。事業立地については、[事業の予定はビジネスの型と事業立地【高収益化・生産性向上対策No.2】]をご確認ください。
特に、新しい事業を作るときは右肩上がりに伸びるとしても1次曲線にはならず、多少の沈みを経験しながら、良い事業であればグンと伸びあがります。ゴールまでどんな曲線を描くかは表計算ソフトでは計算できません。
一方である程度予測通りにいくものもあります。それは自分が主体になるもの、例えば経費の執行です。投資をする、人を雇う、事務所を借りる、販促費を使うというのは少なくとも主語は自分です。真面目な経営者であれば、外れたとしてもせいぜい5%~10%に収められるでしょう。売り上げと違い、予想の半分や3分の1になるということはないはずです。
このように、コントロールできることは完全にコントロールすることが経営の目標です。頑張ってもコントロールできないことはあります。例えば時流です。これをコントロールしようとするとおかしなことになってしまうので、勉強して流れを読み適合していくしかありません。
一方自分が執行する、主語が自分になるものはコントロールできますから、これをできるだけコントロールするということ。これが経営者としての執行面における実力でしょう。
次に、頑張ったらコントロールできることの項目を増やして、より全体の中でコントロールできるシェアを上げていくことです。その比率上げていくこともまた、経営管理の延長であり、執行力の腕前の差が現れると思います。
現状をしっかりと認識すること
3つ目として、これが一番大切かもしれませんが、起点、つまり現状をしっかりと認識することです。経営者が一番やってはいけないことは「ないものねだり」であり、「もっと資金があれば」、「もっとよい人材がいれば」と考えるほど無駄なものはなく、責任放棄です。
ただし、現状を知るということは、悲観をするということではありません。資金力や人材を含め、トータルとして経営力を知り、「力相応」を受け入れること。これが経営者の第一歩です。
一方、ゴールは現状と一回切り離し、プロセスも無視して、あるべき姿、なりたい状態を設定しましょう。最後に起点とゴールをつなぎ、この間の数値計画を決めます。数値計画を決めれば、資金繰り計画や、それに応じた人員の増強計画とか、工場の都市計画とか、設備投資の計画といったことが見えてきます。
私も、事業計画を書くにあたり信じているのはゴールだけで、プロセスはあまり自分を信じていません。可能な限り途中は緩めに書きます。
「人間はひとつの事しかできない。それは何かといえば、思いを実現する能力だ」という言葉があります。たったひとつだとしても、思いを実現する力なら持っているのです。
事業計画は、間違っても数字の遊びにならないように、過度に誇示せず、過度に固執せずに柔軟に対応しながら、それでも大きな目標を変えずに胆力を持って取り組んでいただきたいと思います。