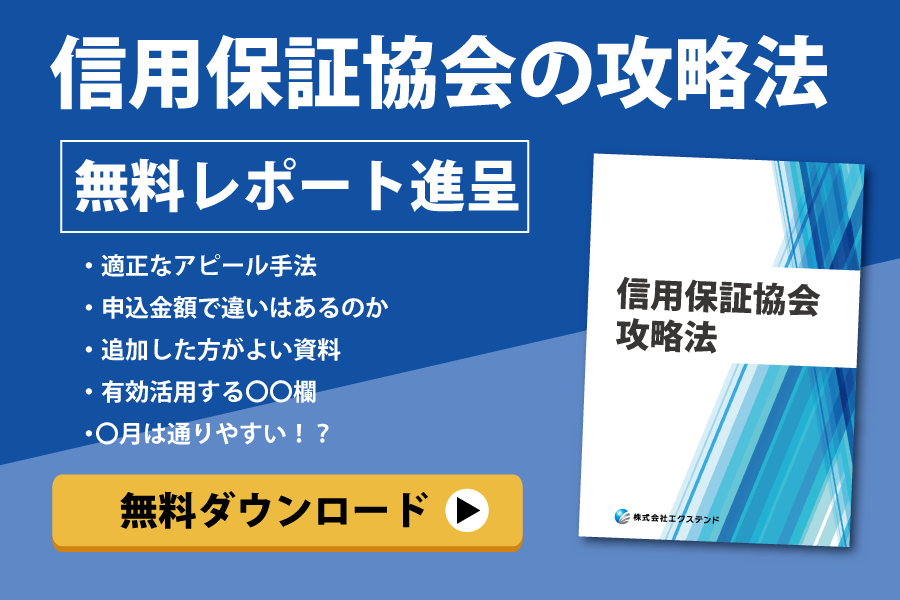保証割合80%の真実|信用保証協会の責任共有制度の影響と例外融資を解説
責任共有制度とは
2007年10月に責任共有制度が開始されたことにより、中小企業の資金調達環境に大きな変化が出ています。責任共有制度とは、それまで信用保証協会保証付融資は融資金額の100%を信用保証協会が保証していたものが、保証割合が80%となり、残りの20%は信用保証協会の保証がなく、貸倒れとなった場合銀行が損失を被る、というものです。
制度の定義
責任共有制度は、信用保証協会が80%、金融機関が20%の割合でリスクを分担する仕組みです。中小企業への融資において、金融機関と信用保証協会が適切にリスクを分け合うことで、より持続可能な金融支援体制を構築することを目指しています。
この制度では、金融機関も一定のリスクを負うことで、より慎重な融資審査と継続的な経営支援を行うようになります。結果として、中小企業の事業性評価がより重視され、単なる担保や保証に依存しない融資判断が促進されています。
導入の背景
従来の100%保証制度下では、金融機関のモラルハザードや、事業性評価が十分に行われないという課題が指摘されていました。そのため、金融機関にも適切なリスク負担を求めることで、より実効性の高い中小企業支援を実現する必要性が高まっていました。
また、中小企業の経営改善や事業再生支援をより効果的に進めるため、金融機関の主体的な関与を促す制度設計が求められていました。責任共有制度は、これらの課題に対応するための重要な施策として導入されることとなりました。
この制度改革により、金融機関は融資先企業の経営状況をより詳細に把握し、必要な支援を行うインセンティブを持つようになりました。経営者の方々にとっては、金融機関からより踏み込んだアドバイスや支援を受けられる機会が増えることになります。
エクステンドでは、経営者からの無料相談を受け付けています。新たな資金調達を成功させたいや、返済・資金繰りが厳しいなどの財務でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。財務コンサルタントが親身になって対応致します。
資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。
制度導入の背景と目的
責任共有制度が導入された最大の理由は、中小企業金融の持続可能性を高めることにありました。2007年以前の100%保証制度では、金融機関が融資審査に十分な注意を払わない事例が見られ、結果として中小企業の経営改善機会を逃すケースが発生していました。
制度が導入された理由
金融機関のリスク分散の観点から見ると、従来の制度では信用保証協会による100%保証により、金融機関の審査が甘くなる傾向がありました。これは結果として、信用保証協会の財政を圧迫し、持続可能な中小企業支援の妨げとなっていました。
中小企業支援の視点では、金融機関が融資先の経営状況により深く関与する必要性が高まっていました。財務コンサルタントとして見ると、単なる資金提供だけでなく、経営改善のアドバイスや事業再生支援といった、より踏み込んだサポートが求められていたのです。
政府の狙い
政府は、この制度を通じて金融機関と中小企業の関係性を、単なる貸し手と借り手の関係から、経営パートナーとしての関係へと発展させることを目指しました。これにより、中小企業の経営基盤強化と持続的な成長を支援する体制を確立しようとしたのです。
さらに、信用保証制度の健全性を確保しながら、実効性の高い中小企業支援を実現するという二つの目的の両立を図りました。金融機関にリスクの一部を負担させることで、より慎重な審査と継続的なモニタリングを促し、結果として中小企業の経営改善につながることを期待したのです。
この制度改革により、中小企業は金融機関からより実践的な経営支援を受けられるようになりました。一方で、審査基準が厳格化する面もあるため、経営者の方々には、より綿密な事業計画の策定や、経営改善への積極的な取り組みが求められるようになっています。
保証割合の変更内容
それまで信用保証協会保証付融資は融資金額の100%を信用保証協会が保証していたものが、保証割合が80%となり、残りの20%は信用保証協会の保証がなく「貸倒れとなった場合銀行が損失を被る」というものです。
保証割合変更の具体的な仕組み
例えば1000万円の融資を行う場合、信用保証協会が800万円、金融機関が200万円のリスクを負担することになります。この仕組みにより、金融機関は融資先の経営状況により注意を払い、適切な経営支援を行うインセンティブが生まれました。
保証割合の変更に伴い、金融機関は融資先の事業性評価をより厳密に行うようになり、経営改善が必要な企業に対しては、具体的な改善提案を行うケースが増えています。
例外的なケース
ただし、すべての融資が80%保証となるわけではありません。特定の政策目的を持つ保証制度では、100%保証が維持されているのです。
創業融資では、新規事業の立ち上げを支援するため、引き続き100%保証が適用されます。創業間もない企業は財務基盤が脆弱なため、手厚い保護が必要とされているためです。
また、小規模事業者への特別小口保証制度も100%保証を維持しています。これは、小規模事業者の資金調達をサポートし、地域経済の活性化を図る目的があります。
セーフティネット保証制度においても、経済環境の変化や自然災害などの影響を受けた中小企業を支援するため、100%保証が適用されるケースがあります。これらの例外的な保証制度は、特定の政策目的や支援が必要な事業者に対して、より手厚い保護を提供することを目的としています。
責任共有制度がもたらす影響
責任共有制度の導入により、金融機関は融資額の20%のリスクを負担することになり、より慎重な審査姿勢を示すようになりました。財務コンサルタントとして、この変化は金融機関の融資判断プロセスに大きな影響を与えていると実感しています。
金融機関が審査基準を厳格化する背景
金融機関は自己責任での融資判断を求められるようになり、企業の将来性や事業計画の実現可能性をより詳細に評価するようになりました。特に、過去の業績だけでなく、今後の成長戦略や経営改善計画の具体性を重視する傾向が強まっています。
また、金融機関は融資後のモニタリングも強化し、経営課題の早期発見と解決支援に積極的に関与するようになっています。これは、貸倒リスクを最小限に抑えつつ、取引先企業の持続的な成長を支援するための取り組みといえます。
貸出状況の変化
審査基準の厳格化に伴い、財務内容や事業計画が不十分な企業への融資は以前より慎重になる一方、成長性の高い企業や経営改善に意欲的な企業への融資は積極的に行われるようになっています。
金融機関は、単なる資金供給者から経営支援パートナーとしての役割を強め、企業の経営課題に対する助言や解決策の提案を行うケースが増えています。これは中小企業にとって、資金調達と経営支援を一体的に受けられる機会の増加を意味します。
さらに、事業性評価に基づく融資判断が主流となり、不動産担保や個人保証に過度に依存しない融資も増えてきています。この変化は、優れたビジネスモデルや成長戦略を持つ企業にとって、新たな資金調達の機会につながっています。
借入希望者への影響
いくら、「今後は良くなる見通しだから」「受注がとれているから」「新規製品は売上が見込めるから」「今までその銀行と長いつきあいをしてきたから」といっても、直近の決算書の内容が悪ければ、融資は困難になります。
では、責任共有制度で信用保証協会保証付融資が受けられなくなってしまった企業はどうすればよいか。キャッシュフローつまり企業が稼ぐ現金で、既存の融資の返済ができているのであればまだしも、そうでなければ、銀行と交渉して毎月の返済金額を抑制してもらわなければなりません。いわゆるリスケジュールです。
借入が難しくなった具体例
決算書の数値が芳しくない企業や、経営改善計画が具体性に欠ける場合、融資の審査に時間がかかったり、希望額を減額されたりするケースが増えています。特に以下のような状況では、借入のハードルが上がっています。
直近3期連続で赤字を計上している企業や、借入金の返済が遅れがちな企業、また事業計画の実現可能性が不透明な企業などは、従来よりも慎重な審査を受けることになります。
企業が取るべき対応策
このような状況に対応するため、経営者の方々は以下のような準備を整えることが重要です。まず、決算書の内容を改善するための具体的な施策を実行に移すことです。例えば、不採算事業の見直しや経費削減、売上向上策の実施などが挙げられます。
融資申込みの際は、より具体的で実現可能性の高い事業計画を提示することが必要です。計画には、市場分析、競合状況、売上予測の根拠、そして具体的な行動計画を含めることが重要です。
また、日頃から金融機関とのコミュニケーションを密にし、経営状況や今後の事業展開について情報共有を行うことで、円滑な資金調達の環境を整えることができます。経営の透明性を高め、金融機関との信頼関係を構築することが、融資を受けやすい体制づくりにつながります。
必要に応じて、外部の財務コンサルタントに相談し、経営改善計画の策定や事業計画の精緻化についてアドバイスを受けることも効果的です。専門家の支援を受けることで、金融機関に対してより説得力のある提案が可能となります。
資金繰り・資金調達など財務でお困りの方は「無料相談」をご利用下さい。
責任共有制度の例外となる融資
特定の政策目的を持つ融資制度では、中小企業への手厚い支援を実現するため、従来通りの100%保証が維持されています。財務コンサルタントとして、これらの制度を適切に活用することで、より有利な条件での資金調達が可能となることをお伝えしています。
特別小口融資
小規模事業者の方々を対象とした特別小口融資では、2,000万円以内の融資に対して100%保証が適用されます。この制度は、小規模事業者の資金調達をより円滑にすることを目的としており、比較的簡易な審査で融資を受けることができます。
セーフティネット保証
経済環境の変化や自然災害などの影響を受けた中小企業を支援するセーフティネット保証も、100%保証が維持されている重要な制度です。突発的な外部環境の変化により業績が悪化した場合、この制度を利用することで、より確実な資金調達が可能となります。
創業融資
事業開始後5年未満の企業を対象とした創業融資も、100%保証の対象となっています。新規事業の立ち上げ期における資金需要に対応し、創業期特有の経営リスクをカバーする制度として機能しています。
その他の100%保証が適用されるケース
事業再生に取り組む企業への融資や、経営改善計画の実行に必要な資金など、政策的に重要性の高い融資についても、100%保証が適用されます。これらは、企業の経営改善や事業の持続可能性を高めることを目的としています。
また、災害復旧のための融資や、特定産業の振興を目的とした融資制度なども、100%保証の対象となるケースがあります。経営者の方々は、これらの制度の適用要件を確認し、自社の状況に合わせて最適な融資制度を選択することが重要です。
これらの例外的な保証制度は、それぞれ特定の政策目的を持っており、通常の融資では対応が難しい状況下における中小企業の資金調達を強力にサポートする役割を果たしています。
利用者が注意すべきポイント
責任共有制度のもとでは、金融機関は決算書の内容とキャッシュフローの状況を特に重視して審査を行います。財務コンサルタントとして、融資を円滑に受けるために必要な改善ポイントをご説明します。
信用保証協会も、審査のウェートの8割は決算書です。しかし、銀行に比べて信用保証協会の審査は、厳しくないのです。なぜなら、信用保証協会は中小企業の発展のために存在するものですから。
ただ、信用保証協会が保証承諾を行っても、銀行が融資を出さない、と言えば、融資は出ません。決算書は、貸借対照表と損益計算書とがありますが、審査で見られる重要なポイントと言えば、貸借対照表においては、純資産合計がどうか、です。ここがマイナスであると、債務超過ということになります。債務超過となると、融資が困難となります。
債務超過でなくても、資産の部で資産価値のない資産が多くあってそれを差し引くと実質債務超過となったり、純資産合計が少なかったりすると、融資審査は厳しくなります。
キャッシュフローは、簡易的に「利益+減価償却費」で計算することができます。
決算書の具体的な改善ポイント
決算書の改善は、売上と利益の両面からアプローチすることが重要です。まず、売上面では粗利率の高い商品やサービスの販売比率を上げることで、収益性を向上させることができます。
経費面では、固定費の見直しと変動費の適正化が重要です。特に人件費や家賃などの固定費は、売上規模に応じた適正水準に調整することで、収益体質の改善につながります。
また、在庫管理の適正化や、不採算部門の整理など、バランスシート項目の改善にも着手することが必要です。これにより、資産効率が向上し、金融機関からの評価も高まります。
キャッシュフローを改善する方法
売上代金の回収期間短縮と仕入代金の支払いサイト見直しを組み合わせることで、運転資金の効率化が図れます。具体的には、早期回収特典の導入や、取引先との支払条件の再交渉などが有効です。
在庫の適正化も重要な改善ポイントです。過剰在庫を抑制し、死蔵在庫を処分することで、資金の流動性を高めることができます。必要最小限の在庫水準を維持することで、キャッシュフローの改善が期待できます。
さらに、設備投資は投資回収期間を慎重に検討し、返済原資を確実に確保できる計画を立てることが重要です。特に、収益性の向上に直結しない投資は、実施時期の見直しを検討する必要があります。
経営計画の進捗状況を定期的にモニタリングし、計画と実績の差異について適切な対応を取ることも、持続的なキャッシュフロー改善につながる重要な取り組みです。金融機関は、このようなPDCAサイクルの実践を高く評価します。
エクステンドでは、経営者からの無料相談を受け付けています。新たな資金調達を成功させたいや、返済・資金繰りが厳しいなどの財務でお悩みでしたらお気軽にご相談ください。まずは下記バナーより「無料相談」をご利用ください。財務コンサルタントが親身になって対応致します。